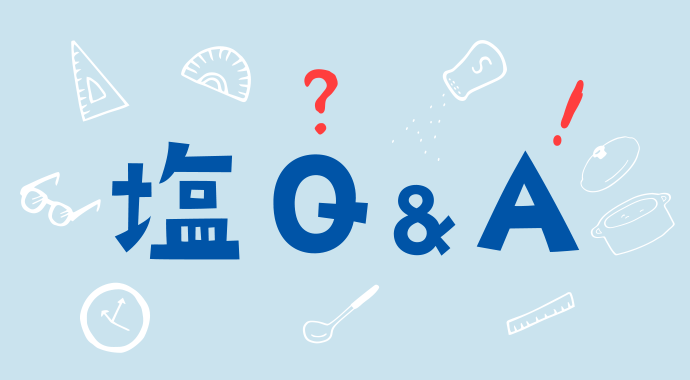
塩の力
-料理編-料理を美味しくするコツは?
塩を使うタイミングや量、効果を知ることです。塩は味付けだけではなく、様々な役割を果たす縁の下の力持ち。ポイントを押さえて上手に使いましょう♪
美味しくするための隠し味
味覚には「甘味」「塩味」「酸味」「苦味」「旨味」の5種類があります。これらは、他の味と混ざった時に味の感じ方に変化が起きます。
例えば、あんこやスイカに塩(甘味+塩味)を加えることで甘みが引き立ちます。このように、異なる2種類の味を混ぜ合わせた時にどちらかを強く感じやすくなることを「対比効果」と言います。出汁に塩(旨味+塩味)を加えることで、うま味が引き立つのもこの効果によるものです。
また、寿司酢や酢の物に塩(酸味+塩味)を加えることで酸味が抑えられるように、どちらかもしくは両方の味を弱める「抑制効果」があります。
何だか味がボヤっとするな…と感じた時は塩を加えると味の変化を感じられるかも♪

シャキシャキ野菜へのひと手間
きゅうりやキャベツなどは、野菜の重さの1~2%の塩(100gの野菜に対して塩ひとつまみ~小さじ1/3)を振って、10分程度おいてから揉むと、水分が抜けて食感が良くなります。また、味が染み込みやすくなるというメリットも。

色鮮やかに、美味しく
青菜やブロッコリーなどは、塩分濃度1.5~2%の塩水(1ℓの水に対して塩大さじ1)で茹でると、塩味がつくと同時に色が鮮やかになります。
また、切ったりんご置いていたら茶色くなってしまった…なんてことありませんか?
皮を剥いたリンゴは、塩分濃度0.5%の塩水(500㎖の水に対して塩小さじ1/2)に3分程度つけ、酵素の働きを抑えて酸化を防ぐことができます。

焼魚には塩がマスト
塩分濃度3~4%の塩水(500㎖の水に対して塩大さじ1)で洗うと、魚の生臭さを抑えることができます。
また、塩を振りかけて焼くことでうま味を閉じ込めて美味さアップ。
一尾のまま塩焼きにする際は、焦げやすい尾ビレや背ビレにも塩をまぶしつけることで、きれいに仕上がります。

パンの美味しさは塩に秘密あり
塩には、生地の弾力や粘りを強くする、風味を良くするなどの役割があります。
塩の入っていないパンはうま味や甘味がなくボソボソとしますが、ほんの少し加えることで仕上がりを大きく変えることができます。
練り込む、振りかけるなど使うタイミングやパンの種類によって、量を調節しながら自分好みのパンつくりを楽しんでみてください。

コシのあるうどんつくりには…
コシのあるうどんつくりにも塩は欠かせません。
塩はほどよい塩味をつけるだけではなく、食感や風味、見た目を良くするために一役買っています。
小麦粉に塩水を加えると、粘りや弾力のもとであるグルテンを強力に引き締めることができ、コシのあるうどんになります。

塩を入れる順番も大事なんです
日本には「さしすせそ」と呼ばれる、「さ(砂糖)」「し(塩)」「す(酢)」「せ(醤油)」「そ(味噌)」の5つの基本となる調味料を指す言葉があります。
この順番で入れると美味しくなると言われており、砂糖は分子が大きく食材に味が染み込みにくいため、最初に入れるのがおすすめです。
塩は水分を吸い出してうま味を引き立たせる効果がある他、分子が小さく染み込みやすいため2番目に入れます。
酢・醬油・味噌は、酸味やコクをプラスする効果があるため、風味が飛ばないように後から加え、「さしすせそ」に入っていない酒とみりんは、砂糖の前に入れることで効果を発揮します。
同じ分量の調味料を加えても、入れる順番によって味だけでなく見た目も良くなるため、コツを押さえると料理が変わってきます。

150年前の梅干しが食べられる!?
150年前の梅干しが現在でも食べられると話題になったことがありましたが、20%以上の塩分濃度でしっかり漬けられていれば基本的には何年経っても食べることができます。
これは、塩が食材の水分を吸い出し、微生物の増殖を抑えて腐敗を防ぐ「脱水・防腐作用」の効果によるものです。


